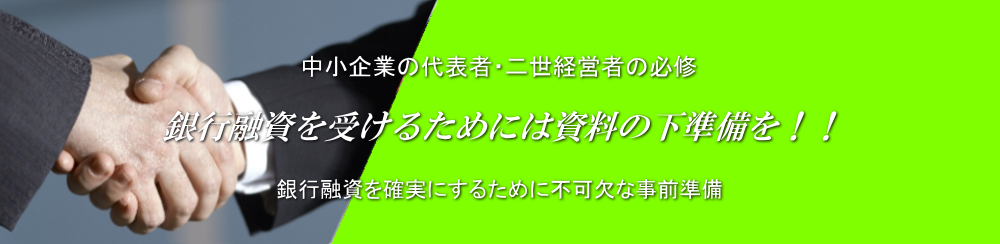オール読物新人賞(文藝春秋社)は今年6月20日で100回目の締め切りを終えた。
オール読物新人賞(文藝春秋社)は今年6月20日で100回目の締め切りを終えた。
下の応募作は第81回目に応募し、落選した作品ではあるけれど、こんなものを書いていたこともあるという見本として、単なる自己満足ではあるけれど、載せてみました。
予選通過作品は、気が向いたら、また日をあらためて載せようと思ってはいますが、長い長い文字の羅列に過ぎませんが、もしよろしかったら、お読みください。
駿河の前は、将門から伽を命じられた。
将門はいつも来客に対して最高の接待を心がけていた。当時、もてなしのなかでなによりも厚いものは、愛妾による夜伽であった。無論強制されてのものではなかったし、愛妾たちも、来客に喜びを与えることをむしろ誇りとさえ思い、嫌な顔も見せずに、伽の勤めを果たしている。伽の拒絶が、来客への重大な侮辱となることも分かっていた。
駿河の前の伽の相手は、秩父郡石間庄の御厨三郎平将平である。異母兄弟ともなると、同じ血筋とはいっても、とかく角突きあわせることが多い。将門が、異母弟将平を敵にまわしたくないのは理解していた。それでもやはり、駿河の前は、将門と血のつながった男と体を交えなければならないことをわびしく、憂しく思った。
武蔵権守興世王・同介源経基・常陸少掾藤原玄茂といった国府の一等官・二等官・三等官たちが引きも切らず、下総石井庄の将門を訪れてきていた。大国の守でも官位は従五位上である。昇殿をゆるされぬ官人だが、赴任した地では、絶大な権力を握っていた。そんな権力者が鞠躬如として訪れてくる。
駿河の前が生まれ育った上野国多野郡小森郷野栗庄にも、国府の役人が訪れてくることがあった。私腹を肥やすことに熱心な彼らは、袖の下を貰うため、どんな山深い郷であろうと、足を運ぶことを厭わない。豪族の娘たちは、訪れてきた都人たちを御簾越しに見ては、彼らの風雅で垢抜けた挙措・言葉遣いのはしはしに胸をときめかす。そんな娘の一人でもあった駿河の前に、下総の豪族平将門のもとで製鉄を司る叔父から、将門の妃にという話が持ち上がった。
将門の館では後宮を真似て、奥御殿の妾たちを、妃と称呼させていた。
将門は、滝口の衛士として都での生活を十年以上も経験したという。都人に憧れていた駿河の前にとって、板東一の頭領とうわさの高い将門の妃となるのは、願ってもない話であった。将門のはからいを得ることで、駿河の前一人ばかりか、一族の将来の繁栄をも約束される。
輿入れの準備もいよいよ調ったある日、従八位上左馬大属として貴族の一端に連なる、異母兄の死の知らせを聞いた。駿河の前は密かに、この異母兄に思慕の情を寄せていた。「昇進も大切だが、人の心や考えを察することのできる美感こそ、より肝要と心得る」。若くして官職を得たことを言祝ぐ駿河の前に答えた、少しばかり風変わりな異母兄の言葉が、ふっと甦る。しかしこのとき、将門への輿入れの憧れが、駿河の前の心を埋め尽くしていた。
将門と一緒に歌を詠い、春には琵琶を奏で、秋には横笛を吹く、そんな目もくらむような奥御殿での生活を夢に見て、異母兄の忌明けを待って、遠く下総までやって来た。しかし、石井庄での生活は、野栗庄のわが部屋で思い描いていたものとは大違いであった。折しも、下総は刈り入れも済み、脱穀の真っ最中であった。女というものは人前で顔をあらわに見せるものではない、そう教えられてきたのに、庭に敷いたムシロのうえでは、北の方桔梗の前を先頭に、他の妃や侍女たちまでが、郎党や下人、雑役の人たちにまで顔を見せて立ち働いていた。
采女として宮廷に出仕させるのを念頭に、儒教はもちろんのこと、和歌創作、そのために、万葉集や古今和歌集ばかりか漢籍や史書にも精通させるべく、日々育てられてきた身には、経験のない農作業は苛酷すぎた。疲労が重なり、怨霊に取り付かれる夢までも見続けたあげく、高熱を出し床に伏してしまったのは、収穫を祝う葉月月見の夜のことだった。大変な所に来てしまった、という後悔の念も、病をいっそう重いものにした。
ところが、多忙を極める将門が、怨霊調伏ため、加持祈祷をする僧を迎えに国分寺へ走ったばかりでなく、毎日部屋に顔を見せては、煎じた薬草を服させ、布を冷水に浸しては額に乗せてくれた。給仕もお付きの女の童任せにしなかった。若い駿河の前にはとても恥ずかしいことだったが、下衣を替えるのを手伝ってくれたり、川屋まで連れて行ってくれたりもした。教養もなく、粗野で乱暴にしか見えなかった将門だが、実際は、驚くほど思いやりが深く、心温い男であることを知った。
笑顔などみせたこともないし、言葉遣いもぶっきらぼうな将門が、時間が経てば経つほど新鮮に感じられてくる。郎党・家人・下僕はもちろん、百姓たちからも慕われ、妃たちの誰もが将門に夢中になる理由も次第に分かってきた。しかしあからさまには出来ないが、駿河の前は不満もあった。確かに将門は、駿河の前をこのうえなく可愛がってくれた。しかし、他にまだ大勢の妃たちがいる。駿河の前は不謹慎なこととは思いつつも、一月三十日のうち三十日三十夜、自分にだけ愛情を注いでくれる相手を、深い意識の底では求めていた。それが叶わぬのなら、せめて将門の子供が欲しいと念じた。
下総に来て暫くの間は、国府の役人たちや豪族たちの給仕に出される度に、俯いて頬を染めるばかりだった駿河の前の目にも、厚化粧の下に隠された彼らの卑小さが、はっきりと見えてきた。風雅を解し、歌なども詠みかわしていたはずの貴族たちが、国司として赴任するや、都人としての教養を放棄して、自ら心なき身に落ちてしまう。受領たちの専らの関心事が、私腹を肥やすことと、女の部屋を訪ねることなのだから、あきれ果てる。
御厨三郎将平も同様で、相伴して酌み交わす将門の目も憚らず、かしづく駿河の前の胸や腰のあたりを粘っこい目で追い続ける。御簾なしに素顔を見られるのはいまだに慣れないのはむろんのこと、しばらく訪れがなかった将門に、前夜抱かれた余韻が残っている肢体を、隅々まで探られているようで、将平の視線が疎ましくてならない。身を固くして目を伏せた駿河の前の姿を追ってくる将平の血走った視線を避けるようにして、いつもなら怖くて決して部屋から出ようともしない逢魔が時に、女の童も連れず裏庭の築山に上った。
高さ一丈(約三メートル)もない低い山だが、遮るもののない頂からは、利根川が蛇行する大平原を越えて、遥か向こうに秩父連山が見通せた。あの山々の向こうに、懐かしい故郷がある。
葦笛を懐から取り出して、そっと吹いてみた。肌身離さず大事に持っていた、異母兄の形見である。葦笛は哀しい音色を築山に響かせた。しかしその音色はすぐに途切れて、北風にかき消された。駿河の前の心は千々に乱れていた。月のものの周期はちょうど子供を授かりやすいときにあたっていた。将平と一夜を過ごせば、身ごもった子が誰の子か不確かなものになる。
築山の廻りをめぐる瓢箪の形をした池の水は、陣屋の周囲を取り巻く壕から取り入れられている。壕は、自然の川を利用したもので、舟を使えばそのまま外に出られる。その壕に、凍えるような北風に押されて現れた一艘の小舟が水辺の枯れ葦の陰に姿を隠すと、やがて庭の裏木戸が音もなく開いた。庭に忍び込んだ人影は、仔爬であった。
仔爬は、蝦夷の末裔である。桓武朝に征夷大将軍坂上田村麻呂の征討により、陸奥胆沢の地から強制的に下総へ移された。新たな土地で蝦夷たちは農耕に従事したのだが、一般農民からは隔離されて、俘囚と呼ばれていた。強制移住から百五十年余を過ぎて、仔爬は生まれた。しかし依然として、状況は変わっていなかった。差別と蔑視の真っ直中で育ったのである。
顔を鉢合せたりすれば、東人たちはいかにも汚らわしそうな表情を浮かべる。そんな彼らだが、蝦夷の娘たちだけは特別らしい。野中で一人歩きする娘を見かけたりすれば、獲物を狙う獣のように忍びより、襲うのである。薄着になる春の衣替えの季節に、それは頻発する。薪拾いに山に入った仔爬の姉の場合も、そうだった。
姉が受けた陵辱を機として、仔爬の東人への憎しみは、一気に燃え上がった。彼の鍛えぬかれた膂力そして残虐非道で執念深い性格といったものも、すべては東人たちへの怨恨から出ていた。少なくとも、発端はそうである。
俘囚仔爬に関心を持った男がいた。従五位上前下総介平良兼、将門の叔父である。良兼は、強力な軍事力を誇る将門を畏怖していた。だから、屈強な兵士を集めるのに躍起だった。東人をあれほど憎んでいた仔爬が、何故良兼の郎党の一員になったのかは不明である。だが、仔爬を配下に入れた良兼は、武勇にすぐれる俘囚部落の若者たちを、徐々に軍に組み入れることに成功していた。
将門と良兼との間には、長年に亙る所領を巡る争いがあった。将門が都にいる間に、相続した土地が良兼に詐取されたのである。勿論、良兼にも言い分はある。将門留守の間、義姉から土地の管理を任され、ただの荒涼とした大地を肥沃な田畑に変えたのは、彼であった。返さなければならない理由など、ないではないか。良兼は開き直り、軍備を着々と整える将門に夜襲をかけようと目論み、籠絡した下人子春丸の手引きで、すでに何人かの兵士を石井の庄に潜入させていた。仔爬も、その一人であった。
仔爬の鼻腔が、微かに漂う香木の匂いをとらえた。匂いは築山から流れてくる。見上げた仔爬の目が、松に凭れて遠くを眺める、駿河の前のなまめかしい立ち姿をとらえた。このとき駿河の前は十六歳。少女期のあどけなさと、男との爛熟の日々が醸し出す色香が入り交じった、春の夜の花のような、妖しいまでの美観であった。仔爬の舌なめずりをする顔が、真っ赤に染まる。願ってもない機会が、向こうからやってきた。
姉が受けた屈辱を晴らすには、極上の東女でなければならない。仔爬は長い間そう思ってきた。それに適った女が、いま目の前にいる。しかし仔爬の念頭にあるのは、東人への復讐の念というよりも、駿河の前に対する醜い劣情だけであり、姉を襲った東人たちと寸分も違いはしなかった。
ひっそりと静まり返る庭を、あらためて注意深く見渡した。誰もおらぬ。しかし、居たのである。池端の岩影に身を潜め、駿河の前の姿に見入る少年を見落としていた。少年も、築山を蛇のように音も立てず上りはじめた仔爬に気づかない。仔爬は仔爬で、近づくほど濃さを増してくる雅な女の香しい匂いに気を奪われて、枯れ枝を踏み折った。振り返った白い顔から、一気に血の気が引く。竦み上がった駿河の前に、歯を剥いて襲いかかった仔爬に、少年が絶叫した。
「わは仔爬だ」
仔爬は駿河の前を羽交い締めにして、喉元に短刀を突きつけた。刀を手にしてどどっと裏庭に駆け入ってきた衛兵たちを、薄笑いしながら睥睨した。あまりにも突然な出来事と、襲ってきた男が放つ凄まじばかりの体臭とで、駿河の前は気が動転した。
「将門の余命は、幾ばくもない」
耳元で囁かれた言葉に、にわかに我に返った。逃れようともがく駿河の前の裾を、男は乱暴にたくし上げた。鉈を手に、必死な形相をして築山を上ってくる少年と、仔爬を恐れて池の端を取り囲むばかりの郎党たちを目の隅で窺いながら、ざらざらとした指で駿河の前の秘部を手荒く弄んでから、陰毛を鷲掴みにして引き抜いた。悲鳴を上げた駿河の前に黄色い歯を見せて笑いながら、指に絡んだ陰毛と粘液を、赤黒い長い舌を出してべろりと舐めとった。
「こいで、なはわのものだ。どこに逃がれようと、そいが教えてくれる」
そう言い残し、仔爬は矢の如く築山を駆け下り、大きな水音をたてて瓢箪池に飛び込んだ。幾重もの波紋を残して、冷たい水中深く、仔爬の姿は消えた。
抜けた髪の毛とか、切った爪、そして化粧道具の小物の一つ一つにさえ、己の霊魂が潜んでいる、と当時の人々はみな信じていた。その大切な分身ともいえるものを、夕暮れどき外にでたばかりに、恐ろしい男に奪われ、しかも飲み込まれてしまった。盗みとられた霊魂は、あの男が生き続けるかぎり、わたしの躰と一つになろうとして、どこまでも追いかけてくる。
仔爬に襲われて築山で落とした、駿河の前の寄る辺でもあった葦笛までが消え失せて、その心細さといったら喩えようもないほどであった。
恐怖を癒す間もなく伽のときがきた。沓音が近づいてきて、部屋の前で止まる。御簾の外から中をうかがい、自分の名を呼ぶ男を、駿河の前は部屋に招き入れた。将平は、女の童がはこんできた酒肴には見向きもせず、青ざめた顔をしてふるえている駿河の前を抱き寄せた。崩れるようにすがりついてきた女の身体のむせるような匂に、欲望が際限もなく膨れ上がる。黙って目をつむっていた駿河の前は、将平が加える愛撫にやがて顔を上気させて、突然、鋭い反応を返しはじめた。駿河の前への将平の執着は、この伽から始まる。
平将門といえば、史実上また巷間、さまざまの伝説を身にまとった人物だが、ありていにいえば当時の革命児といえるであろう。
将門は従四位下鎮守府将軍平良将の総領で、桓武天皇と夫人多治比眞宗(妃は皇族がた、夫人は公卿の女)との間に生まれた式部卿葛原親王の曾孫で、臣籍降下して平の姓を賜った高望王を祖父とする。
地方豪族の子弟たちは、朝廷に登ることを夢見て、みな京に出た。将門の従兄弟(常陸大掾国香の子)平貞盛もまたその仲間であった。将門もまた縁故を頼り、左大臣藤原忠平の口利きで、禁裏滝口の衛士となった。しかし、公卿たちがすることは何でも真似しなければ気の済まない他の子弟たちとは違って、化粧どころか、都人が自分の妻や恋人までも賭けて夢中になる、和歌や蹴鞠、貝合わせにも全く関心がなかった。
将門の頭にあったのは、大洪水を毎年のように繰り返す古里の大河、鬼怒川と利根川をいかに治水するかであった。大陸の土木技術を学習しようと、将門は京の周辺に居を構えた韓人たちの元に足繁く通いつめた。鉄器は大地を掘るのに最も有効な道具であり、鐙や轡などの馬具、そして戦に使用する武具にもなる。砂鉄と木炭を炉に詰め、三昼夜連続の作業の後に、火傷だらけになって真赤な鋼の塊を取り出すなど、製鉄技術の収得にも熱中した。
将門は、今日の目で眺めても十分に有能な学習者であった。しかし、技術習得に熱心なあまり、折角時の権力者藤原忠平のもとに身を寄せていながら、官人が決して一筋縄ではいかない存在であることを観察し忘れた甘さが、将門を破局に導くことになる。
帰郷してからの将門は、多忙だった。開墾の指揮を取るために朝早くから荒れ野に出掛け、寒風が吹き抜ける中を馬で走り回り、体中に砂埃を被って、夕方遅く帰ってくる。時には馬から下りて自ら鍬を握り、マコモやアシが深く根を張る大地を百姓たちに混じって穿つ。そして、開発した新田は、重税のために口分田を捨てた逃散者に与え、自営農民として取り立てていった。
関東の農民たちは、国府の役人たちの悪政に、代々苦しめられ続けられてきた。役人たちは、私田の開拓に公民である農民を使い、田植えの時期を失ったとしても、租庸調などの税は抜かり無く徴収した。納米が無ければ定額以上に出挙し、余分の利息を儲ける。そんな農民にとって将門は救世主であった。
良兼との争いはますます激しくなり、承平七年(九三七)には、正妻君女御と御子は、平良兼軍に下総国猿島郡飯沼湖畔での戦で惨殺された。しかし農民たちの期待を一身に担い、板東の独立を企て、兵を挙げた将門だったが、天運は彼に組さなかった。天慶三年(九四〇)如月十四日、平貞盛と下野押領使藤原秀郷の連合軍によって下総国猿島であえない最期をとげる。
逆賊将門に対する朝廷の追求は厳しかった。将門の首が都大路に晒された後も、その年の正月に発布された「将門を討伐した者には朱紫の品(朱は四位、紫は五位、品は位)と田地を、次将を切った者にはその功に従って官爵を賜う」の太政官符は廃止されていなかった。桁外れの恩賞をめざす地方豪族やここかしこの野党の手で、残党狩りは悲惨を極めた。
天慶の乱に参画しなかった御厨三郎将平の秩父郡石間の山深い荘園に、追っ手の目を逃れた将門の妾たちが保護を求めてきた。将平は、桔梗の前と侍女および近習を大滝の別庄に、十二の前を小鹿野の庄に、そして、駿河の前は将平の屋形がある石間の離れに隠していた。
将平が将門の妾たちを匿っているとの密告が、秩父郡司を通して討伐軍の将源経基のもとに入ったのは、皐月中旬のことであった。……討伐軍が妾たちの皆殺しを企んだのは、将門の子を宿していることを恐れてのことだ。
将平の屋形は城峰山の中腹にあった。山頂の見張り台からは秩父の全郷が見渡せ、赤平川と荒川に挟まれた太田条里も望めた。里では田植えがほとんど終わっていた。
その日は朝早くから濃霧が立ちこめていた。その霧のゆえに、水田を踏み越え、皆野や横瀬方面から集結してきた討伐軍が山麓に陣取ったのを将平は気付かなかった。風に乗って流れてくる人馬のざわめきに、将平は慌てた。下人を走らせて、別庄に隠れ住む将門の妾たちのもとへ急を告げ、駿河の前には十四歳の下僕の少年をつけ屋形から落とした。少年の名は介之である。
自分の妾や子供、侍女たちを裏山の岩窟に隠したあと、将平は百人余りの家人と共に屋形に立て籠った。
二刻(四時間)ほど経った後、介之が一人、駿河の前が置き忘れてきたと云う化粧道具を取りに、屋形に戻ってきたとき、戦いは既に終わっていた。戦後処理に残されているはずの兵士の姿が何処にも無い。ひっそりと静まりかえった屋形に、介之は忍び込んだ。
其処此処に、首の無い骸が転がっていた。壁代には血飛沫が飛び、床に血糊がべっとりと付着している。血溜に羽を取られ、逆さまになった虻が、足をばたつかせていた。
離れに倒れた厨子の下に化粧道具の入った絹の包みを見つけ出し、戻りかけたとき、中庭の方から、男たちの嗤笑とともに、啜り泣くような女の細い声が聞こえてきた。几帳の陰に身を隠し、破れ穴から中庭を覗く。
朝霧は既に晴れ、射し始めた薄日が、母屋の廊下に据えられた将平の首を照らしていた。その首の前で、七、八十人の兵士たちが、女たちを陵辱している。将平の妾や、侍女たちである。老女や童女までも衣類を矧がされ、弄ばれている。自分の番が待ち切れずに、自らの手で快感を求めている兵士までいた。
こみ上げてくる吐き気を懸命に飲み下し潤む介之の目に、兵士たちが働く狼藉を平然と見下ろす討伐軍の将が写った。将平の供をして石井庄を訪ねたとき見かけたことのある前武蔵介源経基は、馬上で薄笑いを浮かべていた。鉄漿で染められた黒い歯が、紅を引いた口元から覗く。胴長で、体の割には大きな顔だ。頬骨が高い。一重瞼で、目が細い。眉毛を抜き取り、額の真ん中に二つ丸く墨で描いてある。厚く塗られた白粉は、低い鼻梁の辺りが汗で剥がれ落ち、赤銅色の地が見えた。
経基に、介之は激しい怒りを覚えた。しかし、その激しい怒りも、直ぐに萎えた。将平を郡司に密告したのは、介之である。……妾たちには、恨みは無かった。憎かったのは、将平一人だった。まさか将平一人に、二千もの大軍を引き連れて、討伐軍が押し寄せて来るとは考えもしなかった。
介之を拾ってくれた将平は、かっては何事にも無欲だった。苦労して開拓した新田も、直ぐに農民に分けてしまう。そして、自分は、狭い荘園で我慢していた。だから、農民たちは挙って、将平を神と仰いだ。そんな将平に、介之は新しい時代の息吹を感じ、深い信頼を抱いていた。ところが、農民たちの期待をになって将門が乱を企てても、将平は行動を共にしなかった。そのことも介之にとっては不満であった。しかし、石間に引き籠ったのは、お屋形に何か考えがあってだろう。不問にしてもいい。介之が許せなかったのは、自分にとっての珠玉であり崇敬の念さえ抱いていた駿河の前を、将平がわが欲望の餌食にしたことである。
将平の供をして、将門の石井庄を介之が訪ねたのは、二年半ほど前の承平七年(九三七)極月のことだった。介之は峠道で雪崩に遭って命を落とした瞽女の弟である。将平の乳母が引き取って育てていたのを、出自は賤しいながら、賢くて機転がきき、勇気もあったから、将平は側に置いて使っていた。あの築山で仔爬の毒牙にかかった女性を救おうと、独り夢中で躍り出たのが介之であった。
膝枕をして寝かしつけてくれた姉に似た匂いを漂わせるその女性が、介之の前に座っていた。介之は目を疑った。自分の賄いをしてくれる駿河の前を、介之は呆けたように見つめていた。介之に頬を赤く染めて給仕をする、女の童を見守るその人の、清潔感の漂う均整のとれた容姿、透けるような白い肌、優しい心根を現す、長い睫毛に覆われた一重の切れ長の目、細くすんなりと通った鼻筋、産毛の生える品のいい形をした頬。給仕の後で貝合わせを教えてくれた、うちすいた髪に小袿の、八、九ばかりの女の童も、そして介之を可愛がってくれた将平の妾たちも確かに美しかった。が、駿河の前は、春風とともに天から舞い降りた天女そのものだった。
駿河の前の美しさも、盲目の白拍子である姉の柔らかな肢体が放つ匂いも、実は若い女の性のもつ妖気でもあることに気づいていない介之は、それ以来、駿河の前のことを思うと、胸が締め付けられるようなせつなさを覚えるのだった。石間に戻ってからも、駿河の前の面影をなぞってばかりいた。
将平の屋形にも少なからぬ女性がいた。が、介之はもう、他の女には目もくれない。そんな介之を、将平は女嫌いと錯覚した。石間に逃れて来た駿河の前の下僕に介之が選ばれたいちばんの理由はそのことだった。
憧憬の駿河の前が石間に来ただけでも嬉しいのに、大滝庄に籠る桔梗の前に預けられた女の童のかわりに、側に付けられたのだ。駿河の前が、意外にも、介之を覚えていて、「心強い限り」と声までかけてくれた。その夜介之は興奮して寝付かれないまま、一時でも、お側近くに居たい、というわけもない衝動に駆り立てられて夜半に寝床を抜け出し、駿河の前の離れに足を忍ばせた。
部屋には明かりが灯っていた。澄ました介之の耳に、呻き声が聞こえてくる。何事かと、壁代の隙間から中を覗く。燈台のほの暗い明かりが、紫煙の立ちこめる室内を微かに照らしていた。信じがたい光景が目の前に在った。廊下を忍び足に走り、庭の草むらに崩れ落ちた介之の目の前を、沢山の水玉が浮遊していた。七色に輝く水玉の一つ一つに、高麗縁の畳の上で絡み合う将平と駿河の前の姿が映っていた。
純な彼にとって、それは男と女のあたりまえの行為とは写らなかった。初めて石井庄で駿河の前に出会った日から二年半の年月の間に、彼女は決して汚されてはならぬ存在にまで昇華していた。その駿河の前が、一方的に獣に蹂躙されている。必死になって抗っている駿河の前を、一方的に汚している。そうとしか思えなかった。介之は言いようのない衝撃を受けた。
将平はこれまで何事にも我欲を見せたことはなかった。無欲は人間を気高くする。禁欲を守っている将平に、介之は他のお屋形とは別格の人間を見ていた。深い信頼を抱いていたその将平が欲望の牙を剥き、介之が憧れてやまない駿河の前を汚している。絶望した介之は、その瞬間、将平に対して激しい憎悪と怒りを滾らせた。それが、介之を密告へと駆り立てたのだった。
ともあれ、兵士たちに代わる代わる組み伏せられ、弄ばれる妃たちの姿は、あまりにも無惨であった。覗いていた破れ穴から介之は目を逸らし、唇を噛みながら後ずさりした。
包みを両手で抱え、几帳の陰から退いていく介之の姿を、女の体に飽いて立ち上がった、顎の張った毛深い兵士が目の隅で捕えた。
仔爬であった。
(あんこわっぱに見覚えがある)
仔爬の脳裏に突然、ある考えがひらめいた。地面に置いた刀を掴み取って、後を付けようと歩みかけたとき、屋形に早馬が飛び込んで来た。
「将門の妾の居所が分かった。小宰相、御代の院、車の前、和歌の前、十二の前らは小鹿野庄、桔梗の前と駿河の前の二人は大滝庄だ」
介之を追おうとしていた仔爬が、駿河の前の一言に、ギクリとして足を止めた。
「将平の首は、塩漬けにして京へ送れ。女たちの首は、残らず撥ねろ。屋形に火を放て。何もかも、燃やし尽くすのだ。急げ、急ぐのだ」
慌ただしく下知を出す経基の目が異様に光る。顔にはもう薄笑いはなかった。兵士たちが歓声を上げた。今度は、美形の噂が高い将門の妃たちを自由に出来るのだ。目の前の女たちの躰にはもう用はない。
恐怖に顔を引き攣らせて地面を後ずさりする女たちを、殺戮者たちが追い詰める。抜き放たれた刀に、燃え上がる炎が反射する。閃光が走り、刀が旋回するたび、血飛沫が飛び、次々に首が転がり落ちた。
経基が馬を駆って、石間庄から飛び出した。その後に真っ先に続いたのは、仔爬だった。汗に濡れた髭面の下の筋肉を痙攣させながら、石間渓谷に添った山道を突っ走って下った。
(駿河の前は、わがものぞ)
石井庄で駿河の前を垣間見、その妖しいまでの美しさのトリコとなって、誘拐を試みた。あと一歩というところで介之に見つかり、失敗に終わっている。以来いつの日か、と情念の炎をもやし続けていた。その機会が来ようとしている。他の連中に自由にさせてたまるものか。
坂道を疾走しながら、興奮のあまり、仔爬は身ぶるいした。
石間庄を逃れた駿河の前は、下僕の少年介之に導かれて、古里である多野郡小森郷野栗庄へと向かっていた。
介之が将平から命じられたことは、乱終結のときまで、できるだけ野栗庄の近くで、それも領主には迷惑が掛からないような何処かに、駿河の前を匿うことであった。野栗庄領主である多野郡司は、駿河の前の父で、広大な山林を持った、板東でも有数の製鉄親方である。朝鮮半島から渡ってきた製鉄技術者集団の子孫で、東国開発のため大和朝廷により住んでいた駿河国から霊亀二年(七一六)に武蔵国高麗郡に移され、その後数代前に、砂鉄が豊富なこの山奥の地に住み着いていた。駿河の前の名も、ゆかりの地駿河国に因んでつけられた。
駿河の前は仔爬の影に怯えていた。将門の死を予言し、それを的中させた仔爬が、恐ろしくてならない。厳しい追捕の手を逃れて、秩父石間庄へ落ちてからも、仔爬がいつもどこかに潜んでいて、絶えず自分のことを監視しているような気がしてならなかった。月影に揺れる木々の枝さえも、仔爬の姿と錯覚してしまうほどだった。
今再び流浪の身となって、討伐軍にあの薄気味悪い蛇のように執念深い男の存在を感じ、背筋にまとわりつくような悪寒から一歩でも二歩でも離れようと、介之の後を必死になってついてきた。足は棒のようになっていたが、休みたいとは全く思わなかった。深夜、ようやく志賀坂峠を越えた。眼下に間物集落が望見できる。ここから中里集落へ、さらに明家峠を越えればそこはもう野栗庄。
懐かしい古里を目前にして、駿河の前の張り詰めた気持ちが緩んだ。その途端に、眼前の、青白い月明かりを浴びて果てしなく広がる樹海が、ぐらぐらと揺らいだような感じがした。息が浅くなって、全身に痺れが走る。あと一、二刻の辛抱とは思うものの、歩くどころか、立っていることさえ億劫でならない。駿河の前の脳裏にまたふっと、顎の張った毛深い男の顔が浮かんだ。しかし凶暴で醜悪な顔は瞬く間に真っ黒な帳の中に消え、駿河の前はそのまま蹲ってしまった。耳元で繰り返し呼び掛ける介之の声が、どんどんと遠のき、奈落の底にむかって自分の身体がどこまでも限りなく落ち続けて行くのを感じた。
夜がうっすらと明けはじめていた。山々に立ち込めていた朝霧も、僅かだが、晴れてきていた。何処かで、ウグイスが鳴いた。眼下には、一晩中、川音だけを響かせていた間物沢川が、遙かに流れを見せ始めている。
深い間物沢川から吹き上げてくる谷風を遮るように枝を広げた巨大なトチノキの陰に、山を背に、二畝(六十坪)ほどの窪地があった。窪地には使い捨てになった古い炭焼窯がひっそりと踞っていた。炭窯の後ろに迫る斜面にはシオジやオヒョウなどが繁り、それらの低木をクズの葉が覆い、枝に絡み付いたフジが花を咲かせている。
斜面の中腹でクズの根を掘っていたイノシシが、石を跳ね上げた。石は、乾いた音を立てて斜面を転げ落ちてきて、炭窯の前でドシンと地響きをたてた。
窯口の上半分を塞ぐ釣は既に壊れ落ちていた。炭窯の中は卵形をしていて、奥の方が広い。幅は四尺五寸ほどで、奥行は九尺余り、天井の高さは三尺七寸くらいか。床には枯れアシが敷きつめてある。
その奥の方に、頭を奥に向けて、駿河の前が伏していた。窯口から差し込む光が、床に乱れる垂髪を少し茶がかかったように見せていた。十八というのに顔が大人びて見えるのは、額に描かれた花でんと、熱に喘ぐ口元から覗くお歯黒のせいだろう。半ば開かれた目は虚ろで、ぜいぜいと、呼吸が荒い。時々ひどく咳込んでは、うわ言を繰り返している。一向に快方に向かわない駿河の前の病状に、万が一のことがあったらどうしよう、と介之の体は不安のあまり震え続けていた。病は怨霊のなすしわざだ。霊験のある僧侶の加持祈祷が必要なのだが、いまは薬草に頼るしかない。
炭窯のある窪地の先はなだらかな峠であった。秩父郡坂本集落に通じるその志賀坂峠の東斜面で介之はナズナを摘んでいて、猪倉を見つけた。土砂に埋まって深さは二尺そこそこになっているが、かき出せばすぐに深くなる。丸太を削いで穴底に立ててから、表面を枯れ葉で覆って罠を仕上げる。こうしておけば、あとはイノシシが落ちるのを待つだけだ。獣肉を食すれば、病人に体力がつく。しかし、その前に、まず熱を下げなくては。
万病に効くというナズナだが、生のままで薬効があるものかどうか自信はない。陰干にして煎じる余裕はない。生のまま、引きちぎった葉を頬張ってみる。口の中一杯に広がってきた苦くて青臭い液に、姉の言葉「苦い薬ほどよく効くのよ。我慢して呑みなさい」を思い出し、不安が僅かに薄らいてくるのだった。噛み続けているうちに繊維分だけになったナズナを吐き捨ると、竹筒の水を口に含んだ。
それまではなんの感情も交えずに、ただ駿河の前を治したい一心の介之だった。幼かった頃にしてくれた姉を真似て、いざ薬液を口移ししようとして、躊躇いが出た。顔を近づけようとして屈み込んだとき、駿河の前のはだけた襟から白い胸のふくらみがぞいていた。
駿河の前を治したい、という介之の純な気持ちに偽りはない。しかし胸の谷間から立ちのぼってくる、温かくかぐわしい肌の匂いに、突然、自分の身体の奥からわきあがってきた衝動に直面して、介之は驚き、当惑し、混乱したのだった。
いま相手にしようとしているのは、お前が畏敬してやまない将門の妃だ。将平やあの兵士たちと同じ真似をするつもりか、身の程もわきまえぬ邪恋など抱くものではない、といつもどこかで介之のすることを注視している天の眼が諫める。だからなおさらのこと、介之の心の中に、切なく悲しい羨望が広がっていく。
自分に不安があって、長い間、尻込みしていた。だが、駿河の前の苦しげな様子に、躊躇いを断ち切り、目を閉じて唇を重ねた。その途端、駿河の前が「いや!」と小さく叫んで顔をそむけた。慌てて飛びすさり、表情を窺うと、眉間に皺を寄せ、蒼白になってもがいている。悪い夢を見ての、叫び声だったようだ。寝ても心を休めることのできぬ妃が、哀れでならない。
もう一度ナズナを噛み、水を含んで駿河の前の側にすり寄り、意を決して触れた介之の唇を、今度は避けなかった。
駿河の前の歯と介之の歯があたって、かちっと鳴る。ふっくらとした駿河の前の唇が、介之には焼けているように思えた。事実、病の熱があったのだが、それだけではない。介之の全身を、心地よく鋭い痺れが走り抜けていった。
遠い池面に咲き浮かぶ白蓮の花のような駿河の前を、身分賤しき介之が、いくら手に触れてみたいと望んだところで、そんなことができようはずもない。しかし運命の悪戯としかいいようのない偶然が、その美しい花を介之の手が届くところまで運んできた。そして今、薬草を服させるためとはいえ唇に触れた。そのことが、もちろん意識してのことではなかったが、駿河の前への親昵感を介之に抱かせ、天と地ほどもある身分差を乗り越えさせる遠因ともなった。
呼吸に合わせて流し込むナズナの液を、駿河の前の白い喉がこくっこくっと鳴って飲み干していく。繰り返しナズナを頬張っては口移しし続けていくうちに、薬液に熱を奪われてか、熱かった唇も次第に冷えていった。
介之の舌に微かに触れる駿河の前の舌に、揺らぐ燈台の炎が浮かんだ。空想が広がって、燈台に映しだされた光景は現実味を帯びてきた。……このように口づけしながら、将平の手が駿河の前の裾を割っていた。介之も真似て、怖ず怖ずと大腿に手を伸ばしかけ、途中でやめた。まだ女性との経験のない介之は、そこから先に踏み込むことが出来ない。心臓が激しく鼓動して、喉元で鳴った。
天の眼に己を恥じ、身を離した。激情が過ぎて、介之の心に残ったのは、自分に対する嫌悪感だけだった。
重い悔恨が広がっていった。将平も、あるいは将門も、この白い肌の魅力に幻惑されただけではなかったか。将平を聖者と見たのも、一転して獣と憎んだのも、思えばわれの勝手な思いこみにすぎなかった。そんな浅はかな思いこみが、大切なお妃さまを、生き地獄に落としてしまった!。要するに、われは、ただ、美しいお妃を独り占めしたかっただけなのだ。
駿河の前の額からは、いつしか熱が引いていた。荒かった息づかいもだいぶ落ちついて、眉間に寄せていた皺も消えていた。ナズナの薬効があったようだ。息を口でしているのは、鼻が詰まっているからであろう。窯口から差し込んでくる明るい照り返しに、お歯黒のはげたところが、きらきらと光っている。駿河の前の枕元ににじり寄り、寝息を立てる美しい顔を、飽きることなく見つめながら、介之は考えた。
(山にはウサギやイノシシがいる。川にはヤマメやイワナが豊富だ。探すつもりになれば、山菜やイモ、木の実だって、幾らでも見つけられる。帛を打つことさえできるだろう)
だが、将門さまのもとで思うに委せた日々を過ごしてきたお妃さまに、山中での炭窯暮らしが耐えられるだろうか。
(炭窯での生活は、乱終結の官符が出るまでの辛抱なのだ。その期間さえ無事に過ごせれば、お妃さまは自由の身になる。大手を振って野栗庄へ戻れる)
事実、介之の推理は正しかった。西国の方で、伊予国掾藤原純友が海賊の頭となり、不穏な動きをしていた。将門が討たれて既に三ヶ月、朝廷がいつまでも東国のことにとらわれて、拘る余裕はなくなりつつあった。
窯口から吹き込む微風に乗って、遥か遠くから山を越え、勝ち鬨をあげる声が聞こえてくる。介之は耳を澄ました。それは秩父郡大滝集落の方角と思えた。涎を垂らしながら桔梗の前をいたぶる兵士たちの様子が、まざまざと浮かんだ。
昏々と眠り続けていた駿河の前は、太陽がやや西に傾いた申の刻(午後四時)近くになって、やっと目を覚ました。
目に最初に入ったのは、鋭い石の角が無数に突き出た真っ黒な天井であった。頭を巡らせると、沢山の罅の入った粘土の壁がある。所々はげ落ちて、石が覗いている。化粧道具が入った絹の包みと、竹筒が壁際に置いてあった。身を起こそうとした手に、床に厚く敷き詰められたアシの枯れ草が触れた。人が屈んでやっと通り抜けられるほどの入り口から、眩しいくらいに輝く広葉樹の若葉が望めた。
(炭窯の中……)
幼かった頃、異母兄と隠れんぼをしていて、何度か炭窯に身を潜めたことがあった。父と同じように、将門もまた炭を焼き、製鉄も行なっていた。手と足に火傷の痕が残る将門を思い、駿河の前の目の縁から涙が溢れ出た。悲しい夢を見た。手甲をつけ、脚絆を巻き、白い帷子を着て、白足袋に草鞋を履いた将門と君女御が御子を連れて立っていた。
三人を囲むようにして、桔梗の前、十二の前、車の前、和歌の前、御代の前たちがいた。同じように杖を持ち旅支度を整えている。
是非ともご一緒させて欲しい、といくら駿河の前が懇願しても、将門は首を縦に振らない。残れと一喝し、背を向けた将門に、君女御と御子、桔梗の前たちもならい、真っ暗な闇の中を遠ざかって行く。追い付こうとして、駿河の前は懸命に足を動かした。しかし、その足は重く、自由にならなかった。
「お屋形さま、お願いでございます。駿河も、是非ご一緒させてくださいまし」
と叫び続ける駿河の前を、一行の誰一人、振り向こうとしない。
やがて精根も尽き、闇の中を小さく消えていく将門を、ただ呆然と見送る駿河の前は、ふと辺りに漂い始めた体臭に気づいた。立ち眩みを覚えるほどの悪臭、髭だらけの顔、ぬめっと脂ぎって垢だらけの肌……。想像しただけで、背筋を悪寒が走り抜け、手足の震えも止まらなくなる。忍び寄ってくるのが誰なのか、振り返らなくとも分かった。しかし、振り返らずにはいられない。闇の中に膨れ上がる、黄色い歯を剥いた仔爬の顔に、駿河の前は悲鳴をあげた。何百回も、何千回も叫んだ気がした。しかし、気がつくと、仔爬の顔はすでにそこになかった。
何度も何度も叫び続け、喉が乾いて、からからだった。胸も息苦しい。そんな駿河の前の目の前に、一本の柄杓が差し出された。俯いたまま柄杓を捧げている若者は介之であった。まだ色濃くあどけなさの残る顔を見ているうちに、駿河の前の目にまた涙が盛り上がってきた。もぎたての桃の実のように初々しい介之を、ずううとむかしから知っていたような気がする。盲目の白拍子の笛に吹かれて、逆立ちしてみせる黒目の美しい少年……。
将門が討たれてからというもの、何時果てるともない逃亡の生活が続いている。不安と恐怖と絶望に打ちひしがれながら、それでも駿河の前は懸命に孤独に耐えてきた。その疲れ、傷ついた心を、将平はさらに深く傷つけた。傷ついた心を抱え、常闇の中で一人おののきながらも、駿河の前は思うのだった。輿入れする前には輝かしく思えた将門との生活も、結局は落人となるべき深い闇を内包していた。だとするなら、今のこの闇としかいいようのない現実のなかにも、あるいは光が隠されているのかも知れない、と。
柄杓の水は、すこし苦い味がした。しかし、乾いた喉には、それは美味しい水だった。何杯も飲むうちに、体から息苦しい不快感が嘘のように消えていき、目の前を暗く閉ざしていた闇も薄れてきた。それから後、またずいぶん長い時間寝てしまったような気がする。
駿河の前は、窯口を突然塞いだ人影に驚いて、びくっと身を振るわせた。
「お妃さま!」
介之だった。下僕が主よりも先に口をきくのは禁忌である。喜びの余り、介之は法を超えた。が、駿河の前は咎めようともせず、微笑んだまま黙って頷き返した。
窯口から差し込む光が、微かに横を向いた駿河の前の顔に鮮やかな陰影を作った。ぞっとするほどあでやかな姿に、燃え上がる夢が一挙に萎んでしまうほど遠いものを、介之は感じた。一方の駿河の前も、逆光を受けて窯口に浮かび上がった介之の初々しさに、思わず視線を逸らした。
介之が抱えた大きな笊には、食べ物が入っていた。ヤマノイモ、キジの卵、ミズナの根、大きさが一尺もあるイワナ、ワサビ、そして底には炭までが詰まっている。米でも布でも、欲しいものは何でも、どこからか湧き出して来るものと錯覚している都人たち、もちろん自分も含めてのことだが、もしこの大自然の中に放り出されでもしたら、餓死を待つほかはないだろう。駿河の前は、将門とも共通する自然児の逞しさを介之に感じていた。
介之が割ったワサビを、言われるままに噛み続けるうちに、粘りとともに、ぴりっとした甘い味が口の中一杯に広がってきた。と、同時に、きーんという刺激が鼻に抜けた。顔を覆った駿河の前の涙腺から涙が迸り出ると、空気が鼻腔をすうーっと通り過ぎた。爽やかな若葉の香り、沢を迸る水の匂い、何処からか漂ってくる炭焼きの煙。駿河の前は、懐かしい古里の匂いを嗅いだ。
介之が差し出したホウノキの葉の上で、イワナが湯気を立てていた。どのようにして焼いたのかが不思議で、首を傾げる駿河の前に、介之は目をさらに細め、眩しそうな表情をした。口元に微笑を絶やさない、あどけない少年と、暫くここで暮らすのだ。言葉で和歌は詠えなくても、自然と対話ができるこの少年こそ、歌人としての不可欠な資質を、心の内に秘めているのかも知れない。石井庄での目紛しい生活の中で、久しく忘れていた和歌の手習いを、また初心に戻って始めてみよう。駿河の前は、我知らず微かな胸のときめきを覚えていた。
「峠道の向こうの炭窯までいき、煙突で焼きました。澄んだ煙でしたから、木酸の臭いはしないはずです」
炭を焼く窯の近くに人が居なかったのは、炭材を切り出すために山に入っていたからだろう。その煙突から出る煙で魚を焼く、本当に機転の利く子である。
「お召し上がりください」
何も食べたくはなかった。そんな駿河の前の表情に、介之が顔を曇らせるのを見て、一口だけ食べた。すると甘い淡白な味が口の中に広がって、食欲を刺激する。半身を残し、続けて卵とミズナを食べる。竹筒の冷水も美味しかった。食べ終えて、体の中にぽっと火が点ったように感じた。
給仕を終えた介之が立ち上がった気配に、駿河の前は、はっと身を固くした。男が近づくとつい身構えてしまうのは、男を知ってからの無意識の反応だった。それを敏感に察した介之の顔に浮かんだ深い一瞬の愁いの色に、駿河の前は自らを責めた。笊を抱えて脇を通った介之の体から、甘酸っぱい匂いがした。将門や将平と違う、爽やかな匂いだった。
石を囲った中に炭を並べてから、灰でくるんだ熾きをアシの葉の包みから取り出して、炭の上に置き吹きはじめた。
火をつけることに熱中している、ひたむきで純粋な介之の姿を見つめるうちに、駿河の前は、久方ぶりに、心の和みを感じてくるのだった。
「今夜はこれで、もう安心でございます」
火を焚いたりして、煙を発見されば、隠れていることが人に気づかれてしまう。だから、この三日というもの、火の気のない夜を過ごした。初夏とはいえ山中の窯の中は、寒気がきびしかった。アシの枯れ葉で、窯口を覆って、漸く寒さを防ぐことができたのである。
炎を上げはじめた木炭の火に、駿河の前の背中が、ぬくぬくと温かくなってきた。蒼く澄んだ頬にも、赤みが射し、このうえなく美しい。
輝き始めた駿河の前に、介之はうっとりと心を奪われつつも、温かくなるにつれて、沢でブヨにさされた手足や背が、我慢できないほどに痒くなってきた。
仔爬は経基に就いて大滝庄に向かって走った。
大滝庄は荒川最上流の地で、石間からはおよそ五里(二十キロ)、街道の分かれ道に位置する。一方の道は十文字峠を越えて信濃へ、もう一方の道は雁坂峠を越えて甲斐に至る。
荒川の崖縁に沿った山道を疾走すること一刻(二時間)余、漸く、木の間隠れに廃寺が見えてきた。朽ち果てた門前に立つと、山の中腹で陽を浴びる大滝庄が望めた。
額から流れ落ちる汗を手の甲で拭いながら、走ってきた道を振り返る仔爬の耳に、人馬のざわめきはまだ遙かに遠かった。からからの喉が、呼吸する度に、ひーひーと鳴る。大滝庄に忍び込むのは、まず喉をうるおしてからだ。
河原に目を投げると、河原の中程を、川が細々と蛇行して流れていた。仔爬は、岩陰を伝いながら、水辺に忍び寄って行った。異常に気づいたのは、腹這いになって、水を飲もうと水面に顔を近づけたときだった。川の水が血の色に染まっている。
(経基が殺されたのか……)
河原に目を凝らし、経基の姿を探すのだが、どこにも見あたらない。
経基の命がどうなろうと仔爬の知ったことではない。だが、経基一人が流した血で、川がこうも赤く染まるはずもない。
(まさか、そんなばかなことが)
突如生じた疑心に、仔爬は渇きを忘れた。流れを染める血の色をたどりながら、河原を駆け、浅瀬を渡って、上流に向かって突き進んで行った。やがて、紛れもない血の臭いが鼻を衝いていてきた。そしてついに、浅瀬の水の上にかぶさるようにして倒れ伏す、夥しい骸を発見したのであった。
川の水を赤く染めていたのは、自害してはてた女たちが流す血であった。
悪鬼のごとき形相で、骸のひとつひとつを覗き込んでは確認する仔爬。しかし、目指す女は居なかった。どう探しても居ない。躰にたぎる情念の炎は、居ないとなると一層燃え上がる。
(あのとき閃いたおのれの直感のままに、こわっぱの後をつけるべきだった……)
と、そのとき、仔歯は、砂州で小さな骸が動くのを見た。うちすいた髪に小袿の清げなるあの女の童なら、あるいは駿河の前の行方を知るやもしれぬと、走り寄る。
仔爬は瀕死の女の童の小さな肩をむんずと掴み、乱暴に揺らしながら、声を張り上げた。
「駿河の前は何処だ」
女の童が何かを呟いた。仔爬が耳を澄ます。
「すけ、ゆ、き……」
確かにそう聞こえた。人の名前か? もう一度、仔爬が怒鳴る。
「駿河の前だ、駿河の前は何処にいる。言え!」
「いさ、……」
女の童は息絶えた。仔爬の口元に微かな笑いが浮かびあがった。女の童はきっと、石間、と言おうとしたに違いない。
河原にぞくぞくと集まり始めた兵たちに、経基が馬上から声を張り上げた。
「乱は終結した」
勝ち鬨があがる。仔爬は、恩賞を目的として討伐軍に加わったわけではない。朝廷が約束する官爵など、まったく関心がなかった。仔爬の関心は、駿河の前ただ一人であった。
(わの戦は、まだ終わってはおらぬ)
仔爬はついに単身、探索の途に出る決意をした。
山の夜は早い。トチの葉の隙き間越しに、つい先ほどまで目映いばかりの輝きを見せていた山の斜面も、陰り始めていた。羽音を立てて飛び込んできた黒褐色のアブが、窯の中で二度、三度と円を描くと、また何処かへ慌ただしく飛び去っていった。山の頂の残照も消えて、漆黒の夜が、再び訪れようとしている。
汗ばむほどに温かい窯の中には、ノビルの臭気が立ち込めていた。腰の辺りまで麻衣を下ろした介之の背中にできた、ブヨに刺された紅班に、ノビルを指で搾っては、駿河の前が塗っている。
指先が、介之の体に、密かな変化を促し始めていた。
しかも、背後から漂う生身の女の匂い……。
既に男を知る駿河の前である。体を震わせている介之の心の変化は、手に取るように分かっていた。その先にどんな行動がおきるかも。そして、こうしたことは、石間庄を逃れたときから心の底で予測していたように思う。
駿河の前は、将門の子を宿していた。 将平の夜毎の荒々しい扱いにも拘わらず、御子は無事に育っている。それだけ生を望んでいるのだろう。なおさら、愛しさがます。
(どうしても、生みたい)
乱終結の官符が出るまでは、父に迷惑がかかるので古里には帰れない。それまでは、若い二人だけの逃避行だ。介之に頼らざるを得ない今、いくら主従の間だと云っても、既に立場は逆転している。求められれば、どんな嫌な相手でも抗えない。まして、寝ずの看病をしてくれた。食べ物だって持ってきてくれた。逞しく、しかも幸いにして好もしき若者である。
しかし今、駿河の前の心を掠めた感覚は、男と女の逃避行の中から生まれてくる致し方のない交わりの感傷とはすこし違っていた。駿河の前を見つめる介之の顔と、初恋の異母兄の面影とが重なって、これまでに感じたことのない、われとわが心の不思議な揺らめきに戸惑う。駿河の前はぼんやりと感じ始めていた。我が心の全てを寄せることのできる相手を漸く見つけたのかもしれない……と。
窯外の闇に飛び違う、幾筋もの光があった。入り乱れてすうっと光っては消える夏虫が、殺された将門の妃たちの浮かばれない魂の集まりに思えて、駿河の前は怖かった。
山犬の遠吠えがして、突然現れた黒い大きな影が、光る青白い目で、窯の中の二人を窺う。吹き込んできた風に、記憶に染みついたあの強烈な臭いを嗅いで、ノビルを塗る指の動きが止まり、頬を火照らせた介之の裸の背にしがみついた。背中でがたがた震える駿河の前に、掠れ声になった介之がいう。
「カモシカです」
しかし、例の臭いが、また、鼻腔の奥を刺激した。一つになろうとして、盗まれた霊魂が仔爬をわたくしに引き寄せている。こわい。介之の首に絡ませた駿河の前の腕に、鳥肌が立っている。わななきながら、身体をすべらせると、姿勢を崩した介之の膝の中に、べったりと体を入れた。
「お、お妃さま……」
討伐軍に捕らえられる危機は脱したが、生死を潜り抜けてきた興奮は、まだ駿河の前の体の中に継続していた。しかも、間近に仔爬が迫っている予感が、興奮の度合いを一層高めたのである。怯える駿河の前は、心の拠り所を、年下ではあるが介之に求めた。
「介之。もうお妃さまとは呼ばないで……。今のわたしは、ただの追われる身」
介之は慌てた。介之のすぐ目の前に、きらきらと光る、大きく見開かれた茶色い瞳があった。つややかに濡れた唇の間からは、歯が覗いている。介之はめくるめくほどに、動転した。
「お妃さま……」
「ふう、と呼んで」
言霊信仰が盛んだった当時、名前と人は一体のものと見なされていた。だから呪いをかけられるのを恐れ、他人には名前を伏せた。駿河の前が介之に自分の名前を教えたということは、身も心もすべてを介之に委ねることを意味していた。
「介之、もう野栗庄には帰らなくともいい。このまま、炭窯の中で一生を終えても構わない」
仔爬への恐怖からのがれるためと、女の性の本能に駆られての口走りではあったが、それは実は本心でもあったかもしれない。
空想は夢を手繰り寄せるのよと、志賀坂峠の雪崩で生き埋めになった瞽女の姉から、介之は何回も聞かされてきた。だから駿河の前のことは、石井庄で会って以来、これまでに何度も何度も夢の中で抱きつづけてきた。その思い描いた夢想が、いま現実のものになろうとしている。介之の胸が高鳴った。
「介之は、おふうさまのことが、大好きでございました。今日も、うたた寝をしているときに、おふうさまの夢を見たばかりでございます」
膝の中のふうを介之は怖ず怖ずと抱きしめる。ふうが緊張しているのが分かった。、不器用でたどたどしい介之の抱擁が、ふうの肌の香に、次第に荒々しいものに変わっていく。 ふうは躰に火がつくのを覚えた。痺れにも似た快感が、寄せては返す波のごとく、高くまた低く揺れながら高まってくる。ふうは忘我の瞬間、踏みとどまった。
「介之、待って。お願いがあるの」
この期に及んでお願いとはなんだ、と怒りの表情を浮かべた介之を見るふうの目に、深い悲しみの色が浮かんだ。お腹にいる子のことを話せば、介之はどんな行動をとるのだろうか。やはり将平がしたように、ふうの躰を思う様踏み躙ることで、答えようとするのだろうか。
「お腹にいる将門さまの御子だけは、どうしても生みたい」
ふうの躰から離れた介之が、壁際に踞って、膨れ上がる欲望に耐えている。深く俯いて握り拳を震わせる介之を見るふうの眼差しが、どこまでも優しく、温かなものになっていく。「肝心なのは位階ではなく、人の心や考えを察することのできる美感だ」。異母兄の言葉が、いまふうの胸に甦る。
「介之がいてくれなかったら、わたしはとっくに兵士たちの慰みものになっていた」
ふうは突然跪座すると、帯を解きはじめた。きゅ、きゅ、と帯が擦れる。解き終えてから暫くの間逡巡していたが、瞼を閉じるとぱっと衣を開いた。介之の目の前に、白く滑らかな裸身が晒された。衣を着ているときにはたおやかに見えた体だが、裸身にはしっとりと肉がついていた。介之が幾たびも夢の中で描いていたものよりも、それは、ずっとすっと神秘的な美しさにかがやき、同時に肉感的でなまめしかった。
介之の脳裏にこの年月の来しかたがめまぐるしく浮かんでは消えた。ふうの不幸を導いたのは、ひょっとしたら、介之の夢想が原因だったのかも知れない。介之は座ったままで、ふうににじり寄った。介之の手がこわれものにでもさわるように、前方に少しだけ突き出た腹のあたりにそっと触れた。
「こに新皇さまの御子がおられるのですね」
潤んだ目で、ふうが頷く。そして、何かを吹っ切るようにパッと衣を肩から脱ぎ捨て、枯れ草の上に仰向けになった。ふうの脳裏に絡みついた仔爬の影は、すでに消えていた。
ふうに促されて、介之も寄り添う形で横たわった。この介之なら一月三十日のうち三十日三十夜、自分にだけ愛情を注いでくれるだろう。情愛ある介之が愛おしく、思わず胸に掻き抱く。うち匂うふうの肌の香が、介之の体に、再び密かな変化を促し始めた。白く匂うふうの躰を、介之の手がおそるおそる這う。
「介之……」
ウグイスが鳴いて、また朝がきた。太陽は昇っていないが、谷向こうの山の端には日が射していた。そのところだけ、新緑が輝いている。谷からは間物沢川の早瀬の音が聞こえてきた。
朝日を浴びて輝いている山の端の新緑のように、ふうの顔は生気に溢れていた。窯の中には、よい匂いが立ち込めていた。炭火から一条の煙が立っている。炊かれているのは香木だ。その香りの中で、ふうは化粧をしていた。白粉ばかりでなく、紅を引き、お歯黒もしっかりと塗った。丸い青銅の鏡に写ったふうの顔は磨かれて艶やかさを増し、あだめいて、一層美しいものになっていった。
外で足音がして、窯口のところで止まった。
「お化粧が終わるまで入らないで……」
鏡に向かったまま、ふうが言う。が、返事がない。鏡を傾けて窯口を見た。写っている影は、知らない男のものである。はっと、後ろを振り返る。中を覗いていたのは、顎の下に濃い髭を生やした真四角な顔。あの夢の中でも脅えつづけていた仔爬だった。駿河の前は動けなかった。ただ体じゅうの血がどくどくと脈打っている。歯ががたがたと音をたてた。
男はあのときとは身なりがよくなっていた。泥にまみれて薄汚れた水干を着て、侍烏帽子をかぶっている。が、剥きだしになった腕と臑は毛深かったし体からは、腋臭の強い臭いが漂った。男は黄色い歯をみせニヤッとした。
「そいなところに潜んでおったか」
男は、腰を屈めて窯の中に入ろうとした。
「介之!」
「すけゆき? あ、あんひょろっとした、使い走りか。あんこわっぱが、わにかなうはずもねえ」
男はせせら笑った。そして窯口から顔をつっこんだ。しかし、幅が一尺にも満たない窯口から中に入るのは、がっしりと肩に付いた肉が邪魔をして、容易なことではなかった。水干が裂けてびりびりと音を立てた。やっとのことで潜り抜けた男が、被った侍烏帽子を両手で抱えて、板のように広い背を見せて蹲った。
「痛てえ……」
窯の天井から無数に突き出ている石の切っ先に、不用心にも頭を激しく突き当てたのである。頭からたらたらと血を滴らせた男が、顔を無気味に歪ませて、ふうを見た。
「峠の途中で、クモの巣が張っていない廃道を見つけ、もしやと思って入ってみた。すると、香木の匂いが漂ってきたではないか」
将門が討たれてから、逃亡の日々は三ヶ月にも及んだ。一日たりと心の安まる日はなかった。秩父に逃れてからも、辛い日々ばかりであった。頼った将平は、将門に似ていたのは風貌だけで、実際は気骨を持たぬ、単なる好色家であった。夜毎、ふうは草を炊かねばならなかった。
今日の麻薬と同じで、幻覚効果を生むものとして、当時も「粉を使う」ことがひそかにおこなわれていた。将門は京に留学中、鞍馬山に庵を結んだ修行僧に、いわゆる「妖術」としてこの粉を学んだ。芥子の実を潰して粉にしたもの、と思われる。将平との伽を迫られたとき、駿河の前は、将門からこの妖術を伝えられた。香木にこの粉をまぶして、夜、客室に焚いておくのだ。もしこの粉の助けがなければ、汚らわしい夜伽を勤めることは出来なかったろう。
討伐軍が攻めてきて、石間から落とされたことは、ふうにはむしろ有り難かった。が、あれだけの大軍である。逃げ果せることは不可能に近い。もしうまく逃がれ得ても、農民たちに見つかれば、密告される。捕らえられれば……、仔爬の毛深い顔を思い出して、ふうは鳥肌が立った。
石間渓谷を遡り、土坂峠、杉ノ峠、父不見山、長久保山、坂丸峠、矢久峠の北尾根に添い、険しい山道を、介之の後を必死になって付いて来た。雪崩で死んだ瞽女の碑が立つ坂本の集落を下に見ながら、志賀坂峠を深夜に越えた。それから、たった数日が経っただけである。
戦袴の膝をはだけて寄ってきた仔爬のごつごつと節くれだった指が、本能的に夢中で後ずさるふうの肩を押さえた。仔爬が穏やかに言った。
「戦は終わった」
ふうの怯えた目を、仔爬の黒い目が覗き込んだ。
「討伐軍は、西国に戻り始めた」
その言葉は唐突過ぎた。ふうは、にわかには信じられなかった。
「山を下りようぜ」
乱れた裾の合間から覗く白い肌に仔爬の視線が這う。ふうは思わず膝を固くした。いきなりざらざらした手が伸びて、その膝を撫でた。背筋に、悪寒が走った。手が奥に伸びてくる。その手が下腹部に触れた。ふうは目の前が真っ暗になった。そのとき窯口に人影がした。
「おふうさま!」
仔爬が、振り向いた。
「おふうさま、だと?」
血まみれの髭面が、ぴくっぴくっと痙攣した。
「かやつが、なぜ、なの名を知っているのだ」
ふうの手を掴むと、仔爬ははげしい力でふうを引きずるようにして、窯の外に出た。
「おれよ、駿河の前に、手を付けたな。……許せねえ」
「われこそ、許せぬ」
介之は腰の鉈を抜いて、身構えた。仔爬の手を逃れようともがくふうを、彼は抱え直し、刀を抜き払った。対立したまま、二人の男はじっと睨み合っていた。ずいぶん長い時間が経ったように、ふうは感じた。突然介之の目の色が、きらっと光った。光ったのは、あるいは振り上げた鉈だったのかも知れない。仔爬と介之の間隔は二間あった。獣じみた叫びとともにその距離を、介之が一気に縮めた。が、戦い慣れた男に、介之が適うはずもなかった。それを待っていたように仔爬の体が三尺ほども横に動きざま、太刀が介之の胴を撫きはらった。介之の体が草の上に崩れた。
「馬鹿なこわっぱだ」
地面に倒れ伏した介之を見下ろして、仁王立ちの男は鼻で笑った。
介之のところに行こうと腕の中で死物狂いでもがくふうを、仔爬が思わず放した。駆け出すふう。
「おっと!」
ふうの足元を男が払った。倒れてはだけた裾の間から、太股が朝日の中で一瞬白く光った。にたりと顔を歪めて仔爬は、水干の下に穿いた戦袴の紐に手を掛けた。
「こいから峠を越え、坂本でわとなの祝言をする。が、その前に、ここで……」
怒鳴りつつ仔爬が袴を解き始めたまさにそのとき、ぱらぱらと小石が山の斜面から落ちてきた。イノシシだ。人の頭ほどもある石が凄まじい勢いで転がり落ちてきた。
「おっとっと」
危うく身をかわす。その間に必死でなだらかな斜面を上へ、逃れようとするふう。ちら、と介之を振り返る。血の海の中で、体はかすかに動いている。息はあると思えたが、助けようもなかった。
追いかける男の目に、斜面を登るふうの乱れた裾の間から、白い肌がちらちらとみえる。立ち込める草いきれにも欲情をかき立てられた男は、ふうをめがけて、一気に獣が躍るように襲いかかった。
ふうが本能的に二尺ほども体を横に逃れ、径に伏した。その一瞬の動作がふうを救った。仔爬はふうのすぐ横にころがった……と思ったが、そのままふいっと、視界から消えた。
直ぐ間近で、蚊の泣くような細い声がした。起きあがったふうは、声のする方を覗いた。仔爬は、介之の作った猪穴に落ちたのだった。イノシシを串刺しにするために穴底に立てた丸太の切っ先が、男の尻を深々と貫いていた。黄色い歯を剥いた男の口から、こぼっごぼっと血が溢れ出ていた。手を伸ばし、ふうに救いを求める仔爬の全身に、痙攣が走った。ふうは黙って合掌すると、斜面を駆け下りた。
血まみれの介之を、ふうは膝に抱きかかえた。
「介之」
そのとき介之の口元がかすかに微笑み、頷いたように思えた。ふうの腕の中で息絶えて力つきた介之の手からすべり落ちた葦笛は、異母兄の形見であった。丁寧に磨き上げられた葦笛は、駿河の前に対する介之の深い思いを表していた。ふうは嗚咽をおさえきれない。将門の妃となったのも、介之と出会うためだった。いままでの全ての人生は介之と出会うためのものだった。
「わたしを一人にしないで……」
頬を擦り寄せて啜り泣くふうの涙が、介之の安らかな死顔を濡し続けた。
朝廷が「将門の乱鎮定」の判断を下し、諸国の関を開き警固を解いたのは、天慶三年皐月二十一日である。介之が死んだのは、その日から数えて五日めであった。
「みこさま! 下総のみこさま!」
ふうを呼ぶ人々の声が、明家峠の方から聞こえてきた。しかしその声はふうの耳には入らなかった。
同じ年の暮れ、ふうは男子を生んだ。野栗庄で育てられたふうの子は、二十一年後の天徳四年神無月二日に、京へ上った。「将門の男子現る」の噂に、都人は恐慌をきたし、検非違使が出動するほどの大事件になった。その後、ふうの子は消息を断った。
志賀坂峠の中腹にある炭窯の中で優しく愛しあった駿河の前と下僕の少年介之は、過疎の村、群馬県多野郡中里村大字神原字間物にある古びた小さな祠の中で、いまもひっそりと眠っている。 (了)
「第八十一回オール讀物新人賞応募作品」(落選)(四百字原稿用紙換算七十七枚)