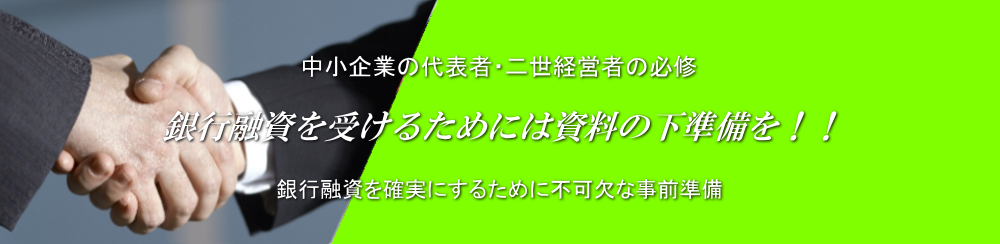山陰地方の私立大学で助教授をしている友人から一昨日、電話があった。
パリに留学する前に会いたい、という。
指定された待ち合わせ場所、東京駅銀の鈴ひろばに行く。
約束の正午には、まだ二十分もあった。
ひろばは混雑していた。少し心配になる。なぜなら、友人と会うのは十四年ぶりである。
互いに年を取った。分かるだろうか。改札口がよく見える場所を探す。
と、背の高い、すらりとした男に目が止まった。
円柱に寄りかかり、『みどりの窓口』の方を向いている。白髪は増えはしたけれど彫りの深い顔は、間違いなく友人である。しかし、(A)目つきが鋭すぎるような気もする。
声をかけようかどうか迷っていたら、目が合い、途端に視線が緩んだ。やはり友人であった。
あいさつもそこそこ。突然に問いかけてきた。
(B)「おれ、泥棒に見えるかい」
妙なことをいう、と思ったが、一歩下がって観察した。
「和製アラン・ドロン」と女の子たちから騒がれていた院生時代よりも一層、容姿は洗練されていた。
黒いシャツの襟からのぞいている渋いスカーフも、板に付いている。
「女心の盗人」になら見えないことはないというと、友人は苦笑いを浮かべ、話し始めた。
予定していた時間より一時間も早く、銀の鈴ひろばに着いた。
喫煙コーナーでタバコを吹かしていたら、改札から私によく似た人が出てきた。
慌てて飛び出した瞬間、床に落ちていた新聞紙を蹴飛ばした。
新聞は、パアーッと広がった。誤解はそのときに生じた。
どこから現れたのか、制服の公安官がそばに立っていた。
そして、週刊誌に読みふけっている、ベンチの女性に声を掛けた。
「カバンが隠されましたよ、お嬢さん」
『みどりの窓口』の前、そこだけ大理石になっている円柱を友人は指さす。
「ああして、ずっとおれを見張っているんだ」。
確かに、柱の陰から冷たく光る目が、私たちの方をうかがっていた。
エッセイの書き方
講評(元朝日新聞記者 斎藤信也先生)
たくさんの誤解、いろいろのエピソードが届きましたが、「犯罪者に誤解された話」はなかった。
なんともユニークでブラックユーモアのような、ちょっと怖さもある作品でした。
いつもながら見事な展開。
フィクションが書けるのでは?と感じています。(すでに手を染められたことがあるのかもしれませんが)
この文にも巧妙に伏線が張ってある。A、Bのところ。
それはまた、サスペンスを生む。
何だろう?と読者はひきよせられてしまう。
そして、いつものごとく終わり近くにパッと意表をつく結末が飛び出す。
結びの一行には、構成とは別の「内容的な」サスペンスがありました。