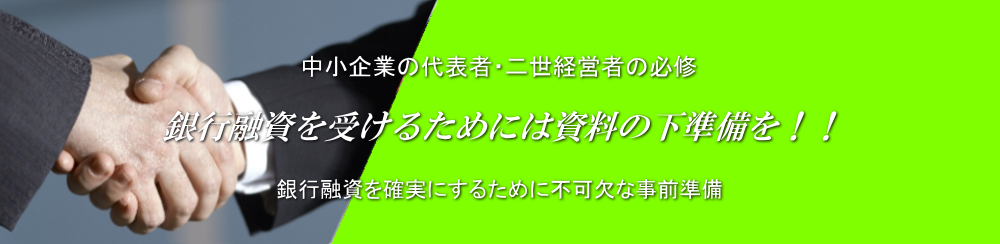「墓参りに行こう」
「墓参りに行こう」
父に誘われて金沢に出かけたのは、落ち葉が舞い散る、三十八年前の晩秋のことであった。母方の墓地は、代々の藩主が頂に眠る野田山の裾にある。早くに男子を亡くした叔父は、無縁仏になるのを恐れ、姓は違うが、姉の長男である私に墓地の管理を委ねた。
―― 戦地から戻った父は、空襲を受けた工場内に野晒しとなったトラック数台を貰い受けて、運送会社をはじめた。昭和三十三年に祖父が亡くなると、群馬県前橋市にある生家の屋敷地、田畑、山林、墓地などのすべてを二男の弟に譲り渡し、野田山墓地の一角に、自分を初代とする墓を建てた。他家の墓地に墓をつくることは墓相学ではよくないといわれるが父は一顧だにせず、開眼供養の法要を終えた墓に、母が和紙に包んで肌身離さず持っていた、私の一歳年下の妹の毛髪と爪を、手のひらに載るほどの小さな白い骨壺に入れて納めた。
白金師(刀の細工師)として市史や県史にも名を残す累代と、いとけない嬰児のまま逝った妹の墓参を終えて、宿泊していた金沢ニューグランドホテルに戻る。螺旋階段を見上げながらロビーに入ると、満面に笑みを湛えて、都内で開かれた個展で何度か顔を合わせたことのある陶芸家の奥さんが待っていた。
 「おひさしぶりやね~」
「おひさしぶりやね~」
案内されたホテル最上階にあるフランス料理店の窓外には、尾山神社や武家屋敷跡、繁華街などの金沢の街々が、曇り空の下に広がっていた。テーブルについていた母娘が、私たちに気づいて立ち上がり、会釈した。御揃いの紫色のワンピースは、二人を年の離れた姉妹のように見せ、透き通るような白い肌ととてもよく似合っていた。
墓参は、三十五歳を過ぎても独身生活を続けていた私を見合いに連れ出そうという、父の策略だった。仕方がない、相手から断ってもらおう。運ばれてきた前菜を、フォークとナイフを使わずに、指で摘まんで食べ始めた。指についたドレッシングを舌先で舐めとりながら顔を上げると、正面に座る娘さんの茶がかかった瞳がじっと見つめていた。目が合う。相手がにっと唇を綻ばせた。心奪われた一瞬である。
「陶芸家の奥様が届けてくださった釣書とスナップ写真は、弟さんのものだったのね。写真の顔はあなたに少しも似ていなかったし、年齢を聞いて驚いたわ。私と十歳も違っていたのだもの。母はあなたのことを一目で気に入ったみたい。でも私は、この人は結婚する気なんかないわと直感した。だから陶芸家の奥さんから、お付き合いしてもいいとの連絡があったときには、信じられない思いがした」
翌年の二月、夫婦円満の神様『尾山神社』の分霊が祀られた、同じホテルの内神殿において、陶芸家夫妻の媒酌のもと、私たちは結婚式をあげた。金沢から嫁を迎えたことを、墓の管理を委ねた叔父は殊の外喜び、披露宴では加賀宝生をじっくりと謡いあげた。
独り身の時には五十六キロしかなかった体重が、美味しい手料理を食べ過ぎて、古希を過ぎたいまでは七十六キロに増えた。肥えたのは主に胴と腹回りで、腕や足の皮膚は弛むばかりである。ソファーに座っていると膝に乗ってくる六歳の孫娘の頬や手足は、肌理が細かくすべすべとしている。細い指先で甲の皺を摘まみ上げ、指先を離しても四五秒間は立ったままでいる皮膚を、不思議そうな表情で見入っている。私も子供の頃、父の手の皺を見て憐れに思えたことがあった。孫娘も、じじを憐れんでくれているのだろうか。
「お義父様と初めてお会いしたとき、御爺様かと思えたほどお年寄りに見えたけれど、七十三歳だったのね。現在の年齢は昔の八掛けといわれるけれど、同じ七十三歳でも、あなたの方がはるかに若く見えるわ。まだ五十代だと思う人もいるかも知れない」
妻はしきりに労わってくれるが、実際は腐り始めたリンゴだ。高脂血症と高血圧の薬を処方され、血中糖度は境界値、絶えざる耳鳴り、毎年繰り返す肺炎。体力がどんどん失われていく。何ということのない平坦な道でも転倒することが多くなった。七十四歳で亡くなった母の年齢にはあと一年、父が黄泉の国に旅立った米寿までは十五年、男の平均寿命までは残り七年。
テレビ時代劇『鬼平犯科帳』で密偵おまさ役を演じた梶芽衣子は、『オール読物四月号』から新連載の自伝で、「いくつになっても挑戦することが大事。そこから未来は拓けていく」と書き記している。文章に取り組んでいると、時間が経つのを忘れてしまう。「趣味のままで十分じゃないの、無理だけはしないで」、と妻からはいわれる。拓ける未来があるかどうかは兎も角として、尾山神社の霊に手を合わせたくなるほど、三十八年間の長きにわたって支え続けてくれた妻の手を、両親のように、ボケで煩わせたくない。文章を書くことは自分を見つめることだ。ボケ防止のためにも文章に挑戦し続け、せめて、もっとましなものが書けるようになってから、閻魔大王と妹に会いに行きたいものだ。
エッセイの書き方