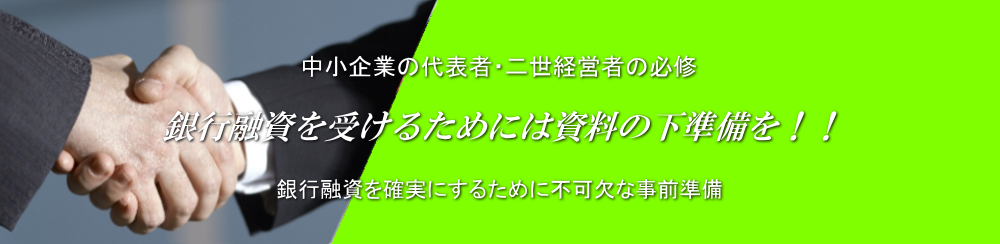年を取ったせいか、夜中に目が覚めることが多くなった。「目を閉じているだけでも身体が休まるから、横になったままでいたらいいのに」、と妻からはいつもいわれる。でも一度目が覚めてしまうと、もう眠れなくなる。隣の布団で寝息を立てている妻を起こさないように、静かに起き上がり、階下のリビングに降りていく。パソコンを立ち上げ、卓上スピーカーのスイッチを入れる。文章を書くのが日課になっている。音楽は、文章を書くのにあたって、なくてはならない道具立てである。
年を取ったせいか、夜中に目が覚めることが多くなった。「目を閉じているだけでも身体が休まるから、横になったままでいたらいいのに」、と妻からはいつもいわれる。でも一度目が覚めてしまうと、もう眠れなくなる。隣の布団で寝息を立てている妻を起こさないように、静かに起き上がり、階下のリビングに降りていく。パソコンを立ち上げ、卓上スピーカーのスイッチを入れる。文章を書くのが日課になっている。音楽は、文章を書くのにあたって、なくてはならない道具立てである。
YouTubeで民族音楽を検索しているときに、セザリア・エヴォラを見つけた。眇で少しばかり太り気味の老いた女性歌手の、心に訴えかけてくるような歌声が好きになって、ここ半年余、飽きもせずに聴き続けている。一九七五年にポルトガルから独立した、アフリカの西沖合に浮かぶカーボベルデ共和国の出身で、同国の盛り場で歌をうたい、食べるのがやっとの生活を送っていた。彼女が四七歳のときにフランスで大ヒットした、「Sodade」の、語りかけるようにして歌う歌詞がどうしても知りたくて、インターネットを検索したら、あった!
「Quem mostra‘bo ess caminho longe? Quem mostra‘bo ess caminho longe? Ess caminho pa S.Tome」。歌詞の下には、セザリア・エヴォラの言葉が添えられていた。「聴衆は私が何を歌っているか、何も分からない。でも、それは問題じゃない。音楽がその全てを示すのよ。彼らは音楽を分かるの」
探し当てた訳詞では、歌の題名を「懐かしい」、そして歌詞を「だれがあなたに示したのこの長い道を 聖トメへ通じるこの道を」となっていたが、哀愁を帯びた甘い歌声に、どうもしっくりこない。Sodadeはポルトガル語で最も美しい言葉のひとつで、日本語には翻訳できない、とも書かれていたが、何百回となく繰り返し聴いているうちに、「追い求めても叶わぬもの」という言葉に思い当たった。そして歌詞の方は、「(幸せを)追い求めて懸命に生きてきたけれど、(幸せになることはついに)叶わなかった。神に授けられた命の灯も、いつしか細くなってきて今にも消えそうだ」、と勝手に意訳してひとり悦に入っている。
感性に訴えて人を感動させるのは文章も同じだろう。書かずにいられない、やむにやまれぬものが心の内になければ、文章に命を吹き込むことはできない。分かってはいるけれど、読む人を興奮させるほどのテーマは、なかなか見つからない。「テーマが見つからなければ、無理をして書くこともないじゃない」、と妻は言うけれど、音楽に耳を傾けていると、空っぽのはずの心の奥底から、小さじ一杯ほどのテーマが、泡のように立ち上ってくる。浮かび上がってきたテーマをじっと見つめながら、ああでもない、こうでもないと直し直しして文章をつくりあげていくうちに、いつしか音楽は耳に届かなくなって、小さかった泡が大きく膨らんでくる。再び音楽が耳に入ってくる頃には、窓ガラスに朝日が眩しいほどに散乱している。
 文章を書くときには、国語辞典と類語辞典のほかに、朝日文庫の『炎の作文塾』を参考書代わりにしている。大学生からの応募作を記者の川村二郎氏が添削して朝日新聞の紙面で紹介した作品を文庫本に仕立てて、二〇〇六年六月に朝日文庫から出版された。
文章を書くときには、国語辞典と類語辞典のほかに、朝日文庫の『炎の作文塾』を参考書代わりにしている。大学生からの応募作を記者の川村二郎氏が添削して朝日新聞の紙面で紹介した作品を文庫本に仕立てて、二〇〇六年六月に朝日文庫から出版された。
「川村二郎さんて、お洒落でとても素敵な人なのね」
婦人雑誌に掲載されていた氏の写真を妻が見つけた。銀座の高級紳士服店でしか手に入りそうもないシックなスーツをさりげなく着こなし、ネクタイの趣味もなかなかの、見るからに男前の都会人だ。服装にうるさい妻がうっとりと目を細めるのも無理はない。
川村氏からは、四十代の頃に受講していた朝日カルチャー通信教育文章教室で指導を受けていたことがある。――「他山の石」(川村二郎氏添削による昭和六十三年七月課題)
私が経営する会社では、父の代から土曜日ごとに役員全員が会議室に集まり、社員食堂の昼食を取りながら意志の疎通を図る(話をする)。
七月四日の土曜日は来客も一緒だった。ところがいつもと違って、運ばれてきた料理はまるで手がかかっていない。給仕していた女子事務員が、「食堂のおばさんがお休みなものですから代わりに私たちでつくりました」と申し訳なさそうに言う。「(おばさん、)ご不幸があったそうです」。(と言われて、)「また!?」。私たちは顔を見合わせた。
おばさんの実家は日航機が墜落して有名になった群馬県多野郡上野村だ。つい五年ほど前までは六人の家族がいた。それが毎年葬式が出て、とうとうおばさんの五十九歳の長兄と、その末っ子で三十三歳になる総領息子の二人だけになってしまった。
息子は働くことが嫌いだった。のらりくらりとして日を過ごしていたが、食べることだけは熱心で、父親の作る三度の飯を、食えないと不平をたらしながら残らず平らげていたそうだ。体は相撲取りと見まがうほどだった。(で、)高血圧と糖尿病が巣くっていた。
昨年の二月におばさんの母親が亡くなった時に、私は式に出て彼に初めて会った。まるでアメーバのお化けだ。怠惰も極まると人間はあのようになるものなのか。あまりの醜さに思わず目をそらした。
七月二日、彼の父親は東京労災病院で左半身のしびれを検査するために、おばさんの家に来て泊まった。その夜、息子から電話があった。「母ちゃんが化けて出た。怖い……。早く帰って」。三日、急いで家に戻った父親は、血だらけの畳の上でうつ伏せに倒れ、事切れている息子を見つけた。警察は他殺を疑ったが、調べると脊髄液に濁りがあり、脳溢血と分かった。
人は自分に似るもの、否、自分の欠点を写し出す他人を憎むと聞く。ひょっとすると、彼は私の分身だったのかも知れない。用心。
――「結びがとてもきいていますね。痛いところをつかれた気がしました。『他山の石』という難題の今回、貴方の作品が内容と表現の両方で、もっとも優れていたと思いました。貴方はこれまでの作品でも完成度がきわめて安定していましたが、今回のが第一だと思います。ほとんど間然するところがありません」。朱がわずか数か所だけ入った講評が、文章を磨き上げる覚悟を固めさせた。食堂のおばさんの実家の跡取り息子も、外見ではのらりくらりと日を過ごしていても、己の不甲斐なさに、嵐のような自己嫌悪が心の中を吹き荒れていたに違いないのだ。考えているだけでは何も始まらないことを教えてくれたのは彼である。文章も実際に書いて、もがきながら、最後まで書き上げてみることが必要なのだ。
書き上げた原稿は第三者に読んでもらえとよく言われるが、私は自己添削をするために散歩に出る。風に吹かれて緑の街を歩いていると、これで完全かなと思っていた原稿に、補うべきところ、不完全なところ、削るべきところ、言わずもがなのところ、もっと相応しい言葉があるのでは、などなどがいくらでも出てくる。翌日散歩に出て風に触れていると、書き直したはずの原稿に欠点が残っていることに気づく。散歩に出て何も頭に浮かばなくなれば、原稿はようやく完成したことになるのだが、日をおいて読み直してみると、粗がまた見つかる。文章とは誠に、「追い求めても叶わぬもの」である。
セザリア・エヴォラの語り掛けるような歌声がどこからか聞こえてきて、はっと目覚める。隣の布団で寝息を立てている妻を起こさないように、静かに起き上がる。
エッセイの書き方