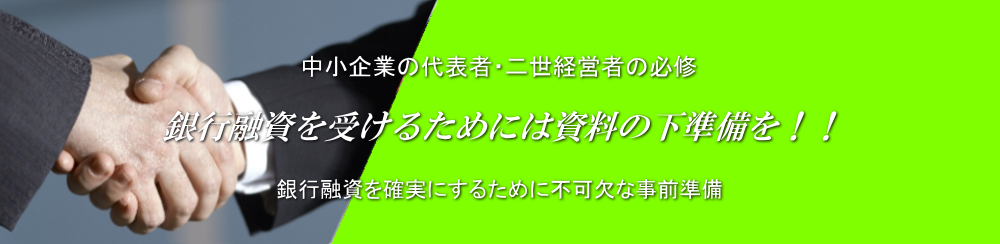亡父が社員を採用するとき作文を課していたのは、わたしがまだ総務課長をしていた遠い昔の話である。
亡父が社員を採用するとき作文を課していたのは、わたしがまだ総務課長をしていた遠い昔の話である。
作文の採点は父がするのではなく、わたしにすべて任された。
文章を書くのは好きだったけれど、どこまでも自分流で、他人が書いた作文に点数をつけることなんて、とても無理だった。
そこで勉強のために自分が書いた作文を添削してもらおうと、朝日新聞の通信講座『文章教室』に入ることにした。
わたしの文章の師である朝日新聞の記者斎藤信也先生と面識を得たのは、通信講座の同窓生たちが年に2度集う、銀座の東京羊羹での対面授業においてであった。
「君なら小説を書ける」と強くすすめてくれたのも先生であった。
藤沢周平を愛読するわたしに、「山本周五郎の小説はもう読んでいることだろうけれど、書くためにはたくさん学ぶところがあるから、もう一度丁寧に読み直してみたらいい」、と教えてくれた。
先生から指導いただいたその日から、書棚にあった『人情裏長屋』・『人情武士道』・『おごそかな渇き』・『花杖記』を取り出し読み始めた。そして読み進むうちに、「天才」にはとても敵わないと思った。
わたしには努力するしか能がない。
もし努力を怠るなら、凡才どころか、一言でいうなら単なる馬鹿にすぎない。
先生には勧められはしたけれど、こんなわたしに小説なんか書けるはずはないではないか。
そんなわたしに書いてみたいという思いを与えてくれたのが、『日本婦道記』のなかの小編『糸車』であった。
わたしを原稿用紙に向かわせるきっかけとなった作品で、何度も読み返しながら、涙がこぼれ出てきてならなかった。
そのときの涙の跡が残る当時のノートを開いてみる。
下手くそで恥ずかしい限りだが、以下のようにまとめられていた。
『糸車』の登場人物
主人公 お高(十九歳) 養女
父 依田啓七郎(松代藩士 五石二人扶持) 二年前に卒中を病み、勤めをひく。
松之助(十歳)
母(松之助三歳の時に亡くなる)
お梶(お高の生母 松本藩士五百五十石西村金太夫の妻)
起
内職で繰った糸を会所にもっていったお高は、係りの老人に「あなたの繰った糸は問屋でも評判だ」と褒められた。帰る途中で父が好物の鰍を買い求め、うきうきした気持ちで家に戻ったのだが、父の態度と松之助の様子が普段とまるで変っていて、不安になってきた。
夕食の後かたづけを済ませ、糸繰りの仕事を広げると、背中を撫でてくれと父から呼ばれる。
撫でていると、「松本の生みの親お梶どのご病気がかなり重く、一目会いたいから来てくれと、使いのものが来た。お前の骨休みにもなるだろうから行ってくるがいい」といわれて、先ほどの松之助の態度を思いやり胸が痛みだした。「ほんの数日のことだ、行ってくるがいい」との言葉に「はい」と答えていた。
承(豊かな生家か貧しい養家に戻るかの「主人公の心の問題」の解決を目指す)
松本の家で泣くような笑顔で出迎えた梶は、病気などではなく、このこしらえ事の中に単純ではない、決定的なものが隠されていることを直感して、お高は呆然とする。
西村の父や兄弟たちと夕食時に引き合わされた広間は、連なる燭台でまばゆいほど明るく、屏風も美しく、幾つもの火桶で部屋の中は暖かった。そして数々の料理。
お高は松代の火桶ひとつの寒々とした貧しい部屋で、二人だけでつつましい食事に向かっている父と弟のことで頭がいっぱいで、夕食が終わると、自分のために用意された部屋に引きこもった。
翌朝、山辺の温泉に行くから用意するようにお梶からいわれるが、菩提寺にお参りに行きたいとお高は請う。菩提寺からの帰り道、弟に自分の生まれた家を案内してもらった。松代の家と大差のない住居だった。
山辺の温泉に行った次の日の夜、明日松代に帰ると言い出したお高に、お梶は松代の父からの手紙を見せる。「両親に孝行を尽くし、西村の娘としての幸せな行く末を祈っている」と書かれてあった。
「お前の生まれた時分は身分も軽く、子供も多く抱え、その日のものにもさしつかえるほど、貧しく苦しい生活だった。人の親として、乳離れしたばかりの子をよそにやらなければならない。どんなに辛く悲しいことだったか。貧に迫られて遣ったお前が、今は自分でその貧とたたかっている。これまでの苦労をいくらかでも償ってあげなければ生みの親として心が済まない」
お梶の言葉を聞きながら、お高は請う返事をする。
「わたしはやはり帰らせていただきます。人の親として子をよそにやることがどんなに辛いことかと仰いました。乳離れをするまでの親子でもそれほどなのに、十八年も一緒に暮らしてきた親子はそうではないとおぼしめしですか」
お高はそういいながらも、子のためには何も押し切ろうとする、親の悲しいほどまっすぐな母の温かな愛のなかに、崩れかかりそうになる心を、お高は懸命に支えた。依田の家を出てその愛を受けることは人の道に外れる。松代に帰ると、お高は繰り返した。
転結
松代に帰ったお高を見て、父はあっという表情をした。
「お高はいちどよそにやられた子です。乳離れをしたばかりで、母の懐からよそへやられたお高を、父上は可哀そうだと思ってはくださいませんか、もし可哀そうだとお思いくださいましたら、ここでまたよそにやるようなことはなさらないでくださいまし」
「西村に戻ればおまえは幸せになれるのだ」
「いいえ幸せとは親と子が揃って、たとえ貧しくとも一椀のかゆを啜り合っても、暮らしていくのがなによりのしあわせだと思います。お高にはあなたが貧実のたった一人の父上です。亡くなった母上がお高にとって本当の母上です。この家のほかにわたしには家はありません、どうぞお高をおそばにおいてくださいまし、よそにはおやりにならないでくださいまし、父上様、このとおりお願い申します」
「父上」
走ってきた松之助が眼に一杯涙を溜めながら、姉と並んでそこへ座り咽びあげた。
「姉上を家においてあげてください。よそへは遣らないでください」
「では家にいるがいい」
松之助は姉の膝にとびついて声を上げてなきだした。
翌朝お高の操る糸車の音が聞こえてくる。
「姉上をずいぶん幸せにしてあげなければならないぞ。姉上はこのちちやお前のためにせっかく幸せになれる運を捨ててくれたのだ、自分のためではない、父とおまえのためにだ」