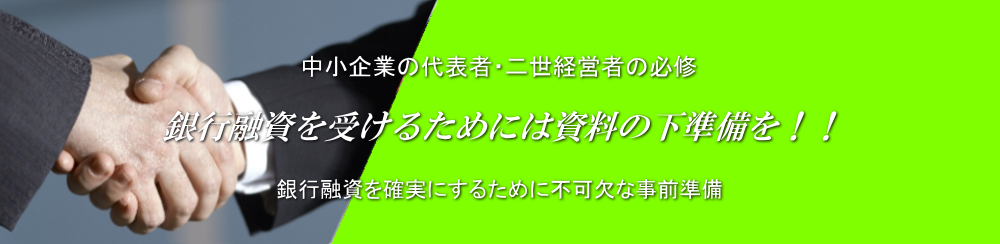祖父の三十三回忌の法要が終わった。
僧からそとばを受け取った父の後ろについて、廊下に出る。
冬の日差しが、本堂から流れ出る香の煙を、明と暗に切り分けている。
目を境内に移す。
赤城おろしがひゅうと吹きつけてきて、私は思わず首を縮めた。
と、どこからか、テンツクテン、テンツクツク、と太鼓の音が聞こえてきた。
先祖が祭られている墓は、寺から五百メートルほど離れた、カシ、クヌギ、ナラなどの木々に覆われた小高い丘の上にある。
太い根が露出して大蛇のように地面をはい、自然の階段を作っている坂道を登っていく。
太鼓は、雑木林の中で鳴っていた。登るに連れて、音は次第に大きくなり、木霊して、四方八方から押し寄せる感じになってきた。
ガサ、ガサ。地面をふかぶかと覆った落ち葉を踏んで男が二人、林の中から現れた。
二人とも、ところどころ擦り切れて白くなった、黒いジャンパーを着ている。
ほおがゲソッとこけた、背の高い方の男が言った。
「せっかく芸を仕込んだってのによお、死んじまいやがった。惜しいことをしたよな。秩父の夜祭りまで、あと十日しかねえぜ」
「いいじゃねえか。ネコなんて、マタタビがありや、いくらでも捕まえられらあな」
血色の悪い顔をした小太りの男は、そう言いながらポケットから一握りの小枝を取り出した。
急な坂道を慌ただしく、半長靴を履いた二人は下って行った。
二人の後ろ姿を振り返って、私は以前、従妹から聞いた話を思い出した。
焼けた鉄板の上にネコを入れた鉄製のかごを置くのだ、という。
熱さで我慢できなくなったネコは、立ち上がってスキップをする。
それに合わせて太鼓をたたく。
数日で、火がなくても、ネコは踊るようになる。
エッセイの書き方
講評(元朝日新聞記者 斎藤信也先生)
拝見する作品、迫力十分でした。
最後のところにきて、がくぜんとし、「その光景」を想像して背筋が寒くなる。
どんな曲馬団やサーカスでも、こんな非情な調教はしないだろう、と思う。
サーカスではたいてい「餌」で釣って仕込む。
動物の「飢え」を手段に使う発想も、ちょっと許せない。
が、このネコのように、ひとつ間違うと焼け死に通じるような「痛み」を手段にする発想、耐え難く「人間の傲慢さ」を覚えます。
ここにもってゆく構成もうまい。
書き出し、まるで無関心なスタート。
法事の話か、とおもいつつ悠々と読んでいくと、太鼓の音、サスペンスが盛り上がり、パタッと止み、二人の男が登場。あとは一気。
そして、意外性のある結末。なかなかにおみごと。