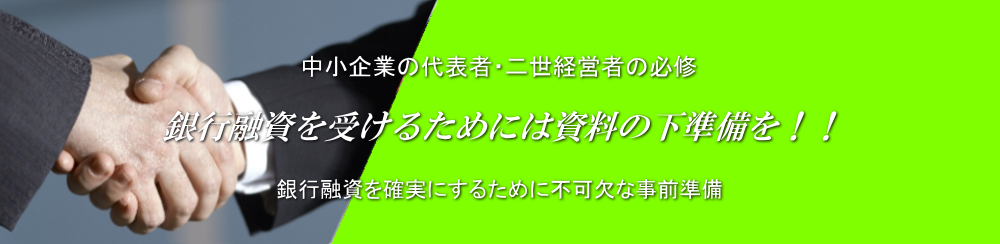江戸城の北の守りとして譜代大名が配置されていた十七万石の城下町川越は、江戸市民の台所、武州の商取引の中心地でもあった。間口三~五間の二階建ての土蔵造りの商家が、目抜き通りには今でも軒を連ねている。
江戸城の北の守りとして譜代大名が配置されていた十七万石の城下町川越は、江戸市民の台所、武州の商取引の中心地でもあった。間口三~五間の二階建ての土蔵造りの商家が、目抜き通りには今でも軒を連ねている。
町のほぼ中央、表通りからちょっと東へ横町を入った左手に、時の鐘がそばたつ。郷土料理の店『くるみ』は、この鐘楼の四、五軒先、江戸時代から続いているというそば屋の裏通りにある。
格子戸のガラスはほこりで曇り、中は薄暗い。商い中の札が下がってはいても一見、つぶれた店のようだ。だから昼食時でも、ほとんど人が入らない。時たま足を止める人も、店構えを見て首を傾げ、立ち去ってしまう。
妻と私はそばが食べたくて、その日が休業だとも知らないで、川越の町を訪ねたのだった。仕方なく蔵造りの町をひとまわりしてみた。しかし食べてみたいと思う店をみつけられないまま、再び『くるみ』のまえまで来た。
『かぼちゃぜんざい』と書かれた張り紙が、格子戸で北風にはためいている。妻は、ぜんざいが好物である。一瞬ためらっていたが、私の手を引き、中に入った。
正面には三畳の和室があって、右手のたたきに、触れるとガタガタする古びたテーブルが三つ。その一つに座って、壁に張り付けられたメニューを見ていたら、白髪ぼうぼうのおばさんが左手のノレンの奥から出てきて、湯飲みを置いた。
くすんだ黄緑のセーターに汚れたエプロンをつけている。すすくさいおばさんだ。
「ぜんざいは売り切れました。本日のおすすめ品は、くるみごはんです」
半ば強制的に、川越の近郊で採った山菜二十八種を使って料理したという、すいとんのついたくるみごはんを注文させられた。
かぼちゃぜんざいを食べそこねた妻は、ベソをかきながら縁の欠けた湯飲みに口を付けた。
そして叫んだ。
「まあ、おいしい」。
入るのにも、入ってからも勇気のいる店だが、くるみごはんもすいとんも、とにかくうまかった。
エッセーを書く(平成五年二月)
講評(元朝日新聞記者 斎藤信也先生)
さて今日の文も、味があった。
何よりも文章のよさ。書き出しのあたり、地形や歴史の説明のあたり、みごとです。
プロの時代小説のはじまりのよう。
書き出しだけでなく、全体に表現が細やかで的確で、目に浮かぶように描けています。
センテンスの長と短の呼吸もいい。
内容も楽しい。
ほのぼのと素朴で、「食べもの雑誌」などのエッセイ欄にのせてもいいような……。