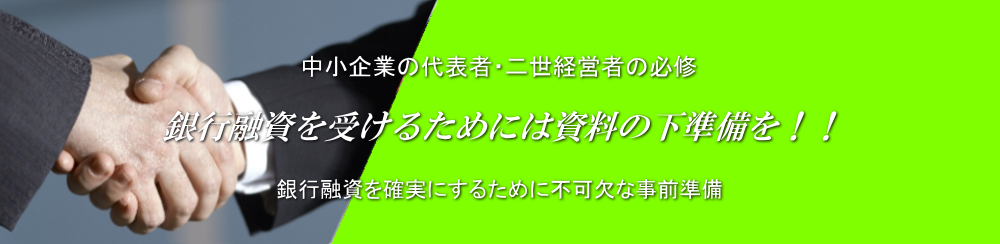夕方近くなって、何の前触れもなく大阪に住む知人が会社へ訪ねてきた。
夕方近くなって、何の前触れもなく大阪に住む知人が会社へ訪ねてきた。
ソファーに凭れると、深いため息をついた。
浅黒い顔に疲労の色が浮かんでいる。
「会議、会議でやんなりまっせ、ほんまに」
彼は四十八歳。大学は出ていない。関西に本社がある上場企業で、営業本部長を勤めている。
「会社をここまでにしたんわなあ、わしらだっせ」
金縁眼鏡の奥の知人の目頭には、うっすらと涙が浮かんでいる。
京大を出た三十八歳の二世が社長になって、会議の回数が増えた。
「二十一世紀の当社」、がテーマだそうだ。
弁が立つ新社長から会議の度に知人たちは、容赦なくやりこめられているという。
「くさりまっせ。あんたはんのように、わしらんとこの社長も、なにもせんでええんです。じっと観察してくれはったらそれでええんです。わしら働くのほんまに好きなんやから」
私も二世経営者である。三十一歳のときに父から会社を引き継いだ。
☆ 二世に対する周囲の期待は大きい。だから、何かをしなければと強迫観念に追いつめられる。
しかし経験不足は否めない。
その不足を埋めようと、高い金を払って勉強会に出たり、たくさんの本を読む。
やがて、二世よりもはるかに経験を積み手練でもある社員が、”新知識”を持たないことから馬鹿に見えてくる。
私もまた、屁理屈で社員たちを困らせた一人だった。
「会議で能書きばかりゆうとったかて、なーんももうからんがな。わしらに任しといて、なんぼでも自分のしたいことやらはったらええんです」
まさか知人の話すとおりにもいかないが、あわてて何かをする必要はないと思った。
学歴と経営手腕とは別だ。
商売の結果である数字を解読する技術と、観察眼を養う訓練だけをしていれば、経営計画を立てることが社長のなすべき最も重要な仕事である、ということが見えてくる。
話すだけ話して時計に目をやると、慌ただしく知人は立ち上がった。
「ほなら、またよらしてもらいますわ」
得意先をこれから接待するのだ、と言う。
自らを励ますような口調だった。
エッセーの書き方
講評(元朝日新聞記者 斎藤信也先生)
今日の文、拝見して、熊井さん社長でしたか。
三十代そこそこで就任された。ご苦労なさったことと思います。
十数年の年月を経て、いま脂がのりきったところでしょうね。
それにしても、社長さんには惜しい筆力!
や、これは失礼、社長族でも筆の立つ人、けっこういらっしゃる。
でも、でも…私の旧友たちの中にも社長や専務けっこういますが、おしなべて「仕事の世界にはくわしいが、筆の方は…」という連中ばかり。
やはりそのタイプの方が、断然多いようです。
☆のところ、実によくわかる。ナルホド、ナルホドと思う。
二世という立場ゆえの、ひとつの側面でしょうね。
これからもご本業に励まれつつ、天与の「筆」のほうもがんばってくださいますよう。